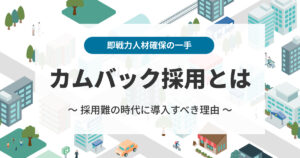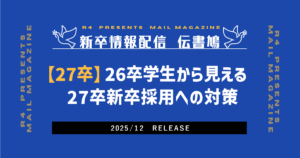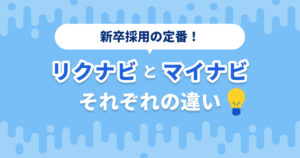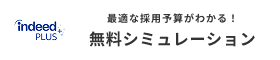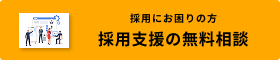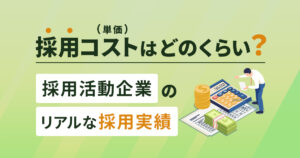フリーランス新法をわかりやすく解説!対象の取引や企業が対応することは?【2024年11月施行】
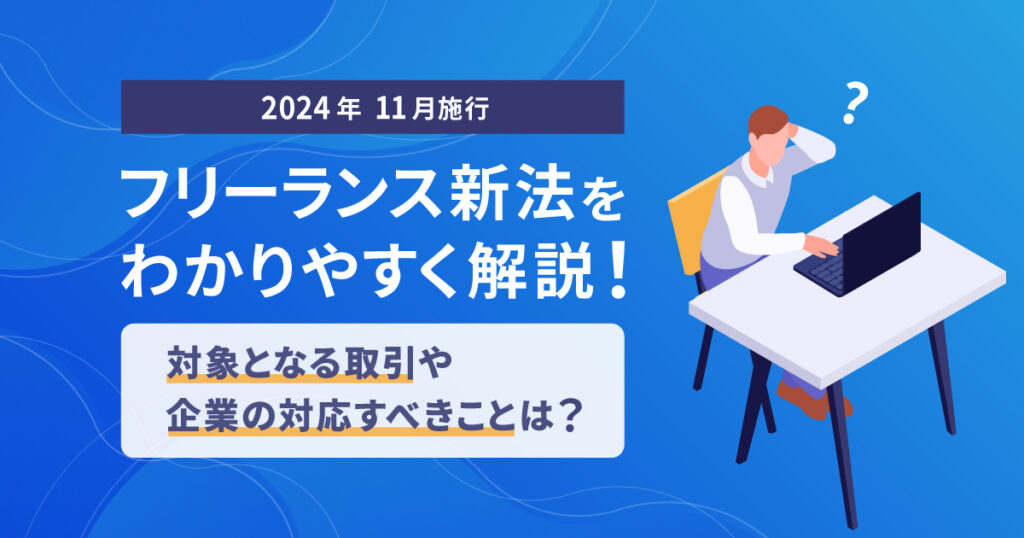
本記事では、フリーランス新法を企業向けにわかりやすく解説します。ガイドラインに基づき、下請法との違いや企業がフリーランス新法に対応するためのポイントを具体例を詳しく紹介します。またフリーランス新法による企業の影響や対応事項についても解説しているため、ぜひ最後までお読みください。
フリーランス新法とは?いつから施行された?
まずは、フリーランス新法とは何かや、いつから施行されたか、フリーランス新法の対象などをわかりやすく解説します。
- フリーランス新法の背景
- フリーランスガイドラインとは
フリーランス新法の背景
フリーランス新法とは、フリーランスとして働く人々の権利を守るために作られたもので、2024年11月1日に施行されました。
連合総合生活開発研究所の調査(2024年)によると、フリーランスの約46.6%は取引相手とトラブルを経験しており、報酬や業務内容が曖昧なまま契約を進めた結果、不当な減額や納品後の報酬支払の遅延などのケースが報告されています。
また、令和4年度フリーランス実態調査結果では、取引先とのトラブルを経験したフリーランスの32.6%が「何も対応せずに受け入れた」25.9%が「交渉したが改善しないまま受け入れた」と回答していることが明らかになっています。
一方で、フリーランス市場は急成長しています。株式会社ランサーズの調査では、本業・副業フリーランスの人口は1,577万人、経済規模は23.8兆円に達しており、取引環境の改善が急務とされています。こうした背景から、取引の適正化を目指し、フリーランス新法が制定されました。
参考『新・フリーランス実態調査 2021-2022年版』発表
フリーランスガイドラインとは
フリーランスガイドラインは、フリーランスとして働く人が安心して業務を進められる環境を整備するために、令和3年3月26日に内閣官房や公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が共同で策定しました。このガイドラインには、フリーランスと取引を行う事業者が守るべきルールを具体的に記しています。
ガイドラインでは、発注する事業者に対し、独占禁止法(優越的地位の濫用)や下請法の規定を守り、フリーランスに不当な不利益を与えないよう求めています。たとえば、「優越的地位の濫用」を防ぐため、報酬や業務内容が曖昧な契約を結ぶことや、不当な返品を要求することを禁止しています。また、クラウドソーシングサービスを提供する仲介事業者が、フリーランスに対して不当に厳しい条件を課す行為も規制対象です。
さらに、同ガイドラインでは、形式的には雇用契約を結んでいないものの、実質的に労働者性が認められるフリーランスについても言及しています。この場合、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されることが明示されています。
フリーランスガイドラインは、企業とフリーランスの立場を平等にし、お互いが働きやすい環境を作るための指針です。企業はこの内容を正しく理解し、取引の公正さを保つ必要があります。
参考:内閣官房「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」
フリーランス新法と下請法の違い
フリーランス新法と下請法は、その目的や適用範囲に違いがあります。
下請法は、発注者が下請事業者に対して不当な取引を行うことを防ぎ、主に「立場の弱い受注者」の保護が目的です。一方、フリーランス新法は取引の適正化に加え、フリーランスの働きやすい環境づくりに重点を置いています。
例えば、下請法では「役務提供委託」(自分の会社ではできない仕事を外部の専門家や会社にお願いしてやってもらうこと)のうち、自社のための業務委託は対象外です。しかし、フリーランス新法では自社のための業務委託も規制対象に含まれます。また、下請法では資本金が1,000万円以下の法人は規制対象外ですが、フリーランス新法では資本金に関係なく規制が適用されます。
さらに、前述のとおり、フリーランス新法では就業環境の保護にも配慮しています。
具体的には、募集情報の正確な表示やハラスメント対策、育児・介護への配慮といった規定などです。
また、支払遅延については、下請法では明確に禁止されていますが、フリーランス新法では支払期日の設定義務として規定されています。一方で、フリーランス新法は継続的な業務委託(1ヶ月以上)が対象となり、下請法は単発の取引も含まれる点も異なります。
これらの違いから、フリーランス新法はフリーランスの権利保護に重点を置き、下請法は取引の公平性を確保することを目的とした法律であるといえます。企業は両法の違いを正確に理解し、適切な対応を取ることで対応が可能です。
なお、フリーランス新法と下請法で共通して禁止されている行為もあります。具体的には、次のとおりです。
フリーランス新法と下請法で共通の禁止事項
- 受領拒否
- 報酬の不当な減額
- 返品の強要
- 買いたたき
- 物品購入やサービス利用の強制など
フリーランス新法の契約期間ルール
フリーランス新法では、フリーランスとの契約期間に応じて、発注者に求められる対応が異なるため、注意が必要です。
とくにポイントとなるのが「1ヶ月以上」「6ヶ月以上」の契約です。
継続的に業務を委託する場合、契約と契約の間に1ヶ月未満の空白期間しかないと、それらは“通算”される可能性があります。
この「通算ルール」によって、気づかないうちに発注者の義務が発生しているケースも考えられます。
契約の積み重ねが“実質的に長期”とみなされることもあるため、契約期間の管理と記録はこれまで以上に慎重に行うようにしましょう。
フリーランス新法によって企業は何が変わる?
ここからは、フリーランス新法によって企業側にどのような影響があるのかを、一つひとつ解説していきます。
次の事項を遵守しなかった場合、企業側は罰則の対象となり得る場合があるため、注意が必要です。
- 支払期日を定める
- 7つの禁止行為の遵守
- 業務と育児や介護などとの両立に対する配慮をする
- ハラスメント対策を整備する
- 中途解除の場合は事前予告と理由開示が必要
支払期日を定める
フリーランス新法により、企業は報酬の支払期日を定めることが義務付けられました。具体的には、企業はフリーランスから物品やサービスを受け取った日から起算して60日以内の、できる限り短い期間で支払期日を定める必要があります。
例えば、10月1日にフリーランスへ仕事を依頼し、10月15日に納品物を受け取った場合、企業は12月14日までには報酬を支払う必要があります。
本業としてフリーランスで働く人にとって、支払の遅延や不透明さは生活に直接影響を及ぼす場合があります。
この規定の目的は、支払期日を明確に定め、報酬の支払までの期間を不当に長くしないようにすることで、フリーランスが安心して働ける環境を整えることです。
7つの禁止行為を遵守する
フリーランス新法では、フリーランスに1ヶ月以上の業務を委託する場合、発注者である企業が守るべき7つの禁止行為が定められています。
7つの禁止事項
1.受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)
2.報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)
3.返品(受け取った物品を返品すること) 買いたたき(類似品などの価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
4.購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)
5.不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)
6.不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)
業務と育児や介護などとの両立に対する配慮をする
フリーランス新法では、発注者である企業に対して、フリーランスが育児や介護と業務を両立できるよう配慮することを義務付けています。契約期間が6ヶ月以上の場合、この配慮は義務となり、6ヶ月未満の場合でも努力義務が課されます。
具体的には…
- 妊婦健診の日に打ち合わせの時間を調整したり、育児や介護のためにオンラインで業務を行えるようにしたりできるようにする
- 子どもの急病などで予定どおり作業時間を確保できない場合、納期の変更を認めるようにする
- また、出産に伴い転居した際には、成果物を郵送やオンラインなどで納入できるようにする
フリーランスが家庭事情に合わせて柔軟に業務を遂行できるようになることで、取引関係の信頼性が高まり、職場環境の改善にもつながります。
ハラスメント対策を整備する
フリーランス新法では、発注事業者に対し、ハラスメント(セクハラ、マタハラ、パワハラ)によってフリーランスの就業環境を損なわないよう、必要な対策を講じる義務が課されています。具体的には、ハラスメントに関する相談対応体制の整備や、再発防止のための措置を実施することが求められます。
また、フリーランスがハラスメントについて相談を行ったことを理由に、不利益な扱いをしてはいけないという規定も設けられています。これにより、フリーランスが安心して問題を報告できる環境が保証されます。
実際の対策としては、事業者が社内でハラスメント防止の方針を明確にすることや、従業員に対する研修を実施することが挙げられます。
契約解除の場合の対応
フリーランス新法における契約解除は、「6ヶ月以上の業務委託契約を解除または更新しない場合、発注事業者には30日前までに解除を予告する義務」が課されています。契約の解除が近づいた際、例外事由に該当しない限り、フリーランスに対し解除日や満了日を知らせる必要があります。規定の日にちまでに告知をおこなうことで、唐突な契約解除に伴う混乱を防ぐことが目的です。
また、解除の理由についてフリーランスから請求があった場合、発注事業者は例外事由を除き、遅滞なくその理由を開示しなければなりません。この開示義務により、フリーランスが不当な扱いを受けることを防ぎます。
ただし、次の場合には例外事由として予告や理由開示の義務が適用されません。
(1)災害などのやむを得ない事由により予告が困難な場合
(2)上流の事業者が契約を解除し、直ちに解除せざるを得ない場合
(3)業務委託の期間が30日以下など短期間である場合
(4)フリーランスに重大な契約違反がある場合
予告の方法は、書面、ファックス、電子メールなどで行う必要があります。この予告義務と理由開示義務を守ることで、発注事業者はフリーランスとの信頼関係を維持し、公正な取引を行うことが可能です。
フリーランス新法で企業が対応すること
最後に、フリーランス新法で企業が対応すること3つを紹介します。
従業員に正確な情報を周知する
企業は、フリーランス新法によって変更された法律の内容を正確に伝えることが求められます。とくに、業務を発注する担当者が法律を理解していないと、フリーランスとの取引で違反を招くリスクがあります。そのため、社内での教育や情報共有が重要です。
具体的な対策として、法律の概要や禁止行為について説明する研修を実施することが考えられます。また、社内向けのガイドラインを作成し、従業員が必要なときに確認できる体制を整えることも効果的です。たとえば、「報酬の減額は絶対に認められない」「納期や取引条件を明確にする」など、実務に直結するポイントを伝えておきましょう。
書面や契約内容のチェック
フリーランス新法では、取引に関する書面や契約内容が重要な役割を果たします。既存の契約書や注文書が法律に違反していないか、細かく確認することが必要です。とくに、報酬の支払期日や業務内容の明記など、法律で定められた条件に従っているかをチェックしましょう。
具体的には、次のポイントを確認しましょう。
- 業務委託の日付、内容、報酬額が明記されているか
- 支払期日が納品日や役務提供日から60日以内に設定されているか
- 契約解除の場合の手続きや事前予告の規定が含まれているか
もし法律に違反する箇所が見つかった場合は、取引相手と協議し、必要に応じて契約内容を修正する必要があります。
契約書に取引条件を明示する
フリーランス新法では、業務委託において取引条件を明示することが義務付けられています。具体的には、契約書で、業務内容・報酬額・支払期日などを明記する必要があります。取引条件を明示することにより、フリーランスが契約条件を正確に把握し、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
たとえば、納品後の支払い期日は60日以内に設定し、契約書に記載する必要があります。また、契約条件に変更がある場合は、事前に書面や電子メールで通知し、合意を得るようにしましょう。これらの対応により、発注者としての責任を果たすことが可能です。
まとめ
フリーランス新法は、フリーランスの保護と取引環境の改善を目的とした重要な法律ですが、企業にとっても新たな課題をもたらしています。現状、フリーランスは法的に「労働者」とはみなされず、最低賃金や労働時間の規制が適用されないため、発注内容次第では過重な負担を与えるリスクがあります。一方で、過度な規制が加わると、企業の発注意欲を削ぎ、結果的にフリーランス側にも影響を及ぼす可能性があります。
新法の施行により、企業は透明性の高い契約や公正な取引の確保が求められる一方で、柔軟性を維持しながらフリーランスとの協力関係を築くことが重要です。フリーランス新法は、取引環境を整備するための「入り口」に過ぎません。企業としては、法令遵守にとどまらず、フリーランスが働きやすい環境を提供することで、より良い信頼関係を築くことが今後の成長につながるでしょう。
カムバック採用(再雇用制度)とは?企業が導入すべき理由と成功のポイント
【27年新卒】26年新卒学生から見える27年新卒採用への対策
新卒採用で失敗しない!リクナビ・マイナビの違いと最適な媒体選定ポイント
お気軽にお問い合わせください。052-212-2007受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちらR4は採用課題に対する支援をしています
母集団形成、採用コストの適正化、採用代行など、
採用活動の「困った」をご相談ください。