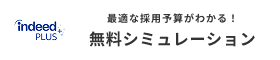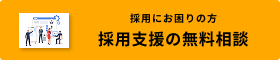R4は自社で生成AIを活用してきたノウハウを活かし、お客様にもご活用いただけるサービスをご用意しています。本ページではR4が生成AI活用に至った背景、現状と成果をご説明します。

生成AI活用の背景
R4はweb制作・開発領域を強化するため、2020年に自社でwebエンジニアを採用しました。その後もう1名エンジニア適性のあった人材が加わり、自社業務の効率化を推進。組織的に業務効率を改善・自動化していくため、2022年にDX推進室を起ち上げました。「SoftBank World」や「Microsoft AI tour」をはじめ、社外のカンファレンスへも積極的に参加して最新情報を掴みながら、システム・プログラムを活用して社内業務の自動化を進めてきました。同年11月にChatGPTが誕生し、DX推進室では積極的に活用をはじめると共に、一部感度の高い社員もChatGPTを使用するように。一方で、さまざまな課題が少しずつ顕在化していきました。
社内でのAI使用で顕在化した課題
- 社内でのITリテラシー格差
- 機密情報や個人情報の漏洩リスク
- 著作権がどこに帰属するのか理解していないままの使用
- 社内ガイドラインが整備されていない
転機になったのは2024年。SBヒューマンキャピタル(株)と出会ったことです。同社はソフトバンク(株)のグループ会社。R4同様のHRビジネスを主事業にしており、かつ、組織的に生成AIの研究もしている企業です。国内でもトップクラスに利活用を進めており、同社グループ内への生成AI展開や政府・教育機関への支援も行っていました。時代の流れを考えると、生成AIの活用が個人・法人共に進み、活用の有無によって生産性が劇的に変わることは明らかです。「組織全体で基本的な知識を身に着け、早期に生成AIを活用できるようになろう」。そう考え、R4では同社とパートナーシップを組むことにしました。
GPTsオペレーター養成講座の受講
まずはSBヒューマンキャピタル(株)の提供する「GPTsオペレーター養成講座」を受講することにしました。対象は全部署から選んだ主要メンバー13名。「生成AI」という言葉に聞き馴染みはあっても、基本的な仕組み、「できること/できないこと」を正しく理解しているメンバーは限られていました。基本的な知識はもちろん、業務に直結したGPTsも各々で作成する全2日間のプログラムを受講することにしたのです。
GPTsとは

ChatGPTを特定の用途に合わせてカスタマイズできる仕組みです。従来のChatGPTは幅広い質問に答えられる汎用的なAIでしたが、GPTsでは特定の役割や目的を持たせることができるため、専用のアシスタントを育てるような感覚で使えます。たとえば営業のロープレ相手として使ったり、企業リサーチに使ったり、社内規定やマニュアルをベースにしたFAQとして使うなど、業務や個人のニーズに応じて柔軟に作成することが可能です。
特筆すべきは、作成過程にプログラミング知識が一切不要という点です。ChatGPTに対して「こういう役割を担ってほしい」と指示するだけで基本的な形は整い、さらに必要に応じて口調や対応範囲を細かく設定したり、自分たちの資料やデータを読み込ませたりすることで、一層実務的なアシスタントへと進化させることが可能。自分たちの業務フローや課題解決に直結させる段階へと進めてくれる仕組みになっています。
プログラム1日目 座学

- 生成AIの歴史
- 生成AI毎の特徴や得意/不得意なこと
- 生成AI活用におけるリスクと著作権
- 実際にChatGPTを触ってみる
プログラム2日目 演習

- 指示に沿ってGPTsをつくってみる
- 自身の業務に使えそうなGPTsをつくってみる
こうしたプログラムを受講することで生成AIの基礎知識を学び、実際に触れてみて、生成AIやGPTsのノウハウを社内へ実装。その後、受講した主要メンバーから全社へ展開していくフェーズへと移行したのです。
生成AI活用における現状
受講後は13名の主要メンバーが中心となって業務に活用できそうなGPTsを作成。約3ヶ月という期間で形になったGPTsは100を超えました。併せて、主要メンバーが各部署で生成AIに関するノウハウを展開。生成AIに触れたことのない部署やメンバーもいましたが、明らかに業務効率の上がった同僚を見て「何でそんなに早くできてるの?」と声をかける姿を見ることが増えました。誰かが生成AIを使っているのを目の当たりにしたメンバーが「それ、何やってるんですか?」と声をかける姿を見ることが増えました。生成AIの活用がはじまると、少しずつですが、着実に、興味を持つ人や活用する人が増えていったのです。そうして、「ごく一部しか使ったことのない状態」から「ほぼ全員が使ったことのある状態」へと進化していきました。

\ 作成されたGPTsの一例 /
| アプリ名 | 概要 |
|---|---|
| ■ 職種理解支援さん | 職種名を入力するだけで、求人作成時に役立つ情報をまとめてアウトプットする。 |
| ■ エリア比較 | 複数エリアを入力すると、人口流出入・年代別人口分布、エリア特性など、エリアの特徴をアウトプットする。 |
| ■ 効果測定カミカゼアプリver1.1 | web広告運用において取得できるデータをインプットすると、表示回数・クリック数・コンバージョン率で注視すべき指標など「分析概要」をアウトプットする。 |
| ■ プロンプトビルダー | 生成AIが理解しやすい形式でプロンプトをアウトプットする。 |
| ■ 新卒採用業務|スカウト文面作成アプリ | 学生のレジュメPDFを読み込ませると、個別カスタマイズ文面を作成。短時間で、学生に寄り添った特別感のあるスカウト文面をアウトプットする。 |
| ■ 履歴書・職務経歴書合否判定 | 指定した合否基準に基づいて合否を判定し、その理由をアウトプットする。 |
| ■ 営業事前準備アプリ | 指定した企業の最新情報を調査し、商談に役立つ事前情報を表形式でアウトプットする。 |
生成AI活用における成果
一人ひとりの業務効率が向上したのはもちろん、お客様へ提供するサービスの品質が向上したのが大きな成果と言えるでしょう。以下に、その一例を挙げさせていただきます。

業務効率が向上した例
- 入社1年目の営業でも、お客様と「業界」や「職種」に関してある程度の水準で対話できるようになった。
- 企業理解や職種理解のリサーチに1h以上要していたのが、数分で完結するようになった。
- web広告のPDCAを回す際の打ち手に困ることがなくなった。
- 人材紹介部門で求職者のレジュメ作成に数十分かけていたのが、数分で完結するようになった。
- ライティング能力に長けていなくても、最低限の求人作成ができるようになった。
お客様へ提供するサービスの品質が向上した例
- 情報やサービスを提供する際のスピードが速くなった。
- 誤字や脱字などがなくなるため情報提供時の品質が安定した。
- 雇用関連法規に関して遵守した求人を安定して提供できるようになった。
また、2025年6月から同時進行でDifyを使った生成AIのさらなる活用もはじめています。DifyはAIを使ったアプリやサービスを簡単に作れるプラットフォーム。機械学習に用いられるPythonなどの言語を用いて開発する必要がなく、直感的な操作で世の中のあらゆる生成AIを活用し、かつ、ワークフローを構築できるサービスです。これによって自社オリジナルのチャットボットの構築、社内データと連携した生成AIの構築、プロンプトデータの蓄積および学習データとしての再活用、生成AIを組み込んだワークフローの構築などが実現可能になります。いわゆるローコードサービスですが、おそらく社内にエンジニアが在籍していなければ、開発すること自体難しかったでしょう。
こうした取り組みは、結果的に第三者からの評価にもつながっています。生成AI活用・推進をするキッカケとなったSBヒューマンキャピタル(株)より「ここまで利活用が進んでいる企業は現時点では存在しておらず、おそらく弊社が関わっている企業群の中では最も進んでいる」という言葉をいただいています。2025年8月現在、R4のエンジニアチームは生成AIの開発・推進を目的に、SBヒューマンキャピタル(株)のエンジニアチームと定期的な情報交換も始めたところです。
もちろん、全てが順調という訳ではありません。ガイドラインの整備を進めてきましたが、新しい技術や使い方が日進月歩で誕生するため最新情報の取得やアップデートが欠かせません。利活用が進んだとはいえ、活用レベルには差が生じています。社内における情報共有にも改善の余地があります。組織的な推進に関して言えば「まだまだこれから」というのが正直なところです。それでも日々改善を続けることはやめません。お客様が抱える本質的な課題を捉え、解決する術を考えることに知恵を絞りたいと思っています。そのために生成AIの利活用は欠かせません。

生成AI導入を検討中のお客様へ
現在、R4ではDX・生成AIに関する経験・知識を活かした「お客様への生成AI導入サポートサービス」も提供しています。SBヒューマンキャピタル(株)との協働サービスですので、ご興味がありましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
※記事内の「画像」および「一部の文章」は生成AIによって制作されています。
お気軽にお問い合わせください。052-212-2007受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちらR4は採用課題に対する支援をしています
母集団形成、採用コストの適正化、採用代行など、
採用活動の「困った」をご相談ください。