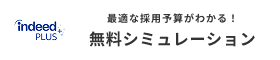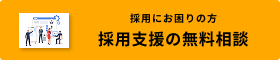採用戦略に役立つ!学生目線で考える採用広報の本音
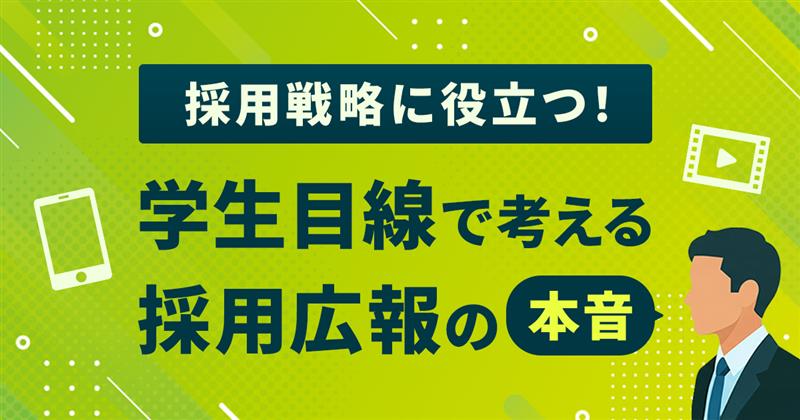
「良い会社なのに、なかなか学生に伝わらない」
そんな採用担当者の悩みの背景には、企業と学生の「見ているポイントのズレ」があるかもしれません。
R4が実施した「ミライカケハシプロジェクト」では、学生たちがR4のアルバイトとして採用広報に携わり、企業の採用課題・手法を考える実践を行いました。
そこから見えてきたのは、学生が感じているリアルな「就活の目線」。
本記事では、その気づきをもとに、採用戦略に活かせるヒントを紹介します。
この記事のポイント
- 企業の意図する魅力と学生が受け取る印象にはギャップがある
- 学生は説明会や社員対応の雰囲気から「大丈夫そうか」を判断している
- 採用広報に学生視点を取り入れることで、採用成功に繋がる
「学生視点」で進めた採用広報の実践
R4が実施した「ミライカケハシプロジェクト」では、学生自らがアルバイトという形で企業の採用広報に携わり、採用アプローチを考える実践型プログラムを行いました。
学生主体で企業の採用広報に挑戦することで、企業が思っている魅力と学生が受け取る印象のギャップを把握し、今後の採用戦略に活かすことが目的です。
プロジェクトの流れは以下の通りです。
学生主体で企業の採用広報を考えた流れ
- 採用ブランディングのケーススタディ
採用広報の意義理解と企画全体の流れを把握 - 新卒採用市場・企業研究のレクチャー・実践
就活市場の現状把握と企業目線での課題理解、情報収集 - インタビューの基本講座・準備
企業担当者への質問設計、ヒアリング方法の習得、訪問準備 - 企業へのインタビュー実施
企業担当者へのヒアリング、魅力や伝えたいポイントの収集 - 情報整理・言語化・提案
インタビュー情報の整理、学生目線での魅力言語化、広報資料・SNS投稿案の作成
参加学生のプロフィールと活動内容
今回のプロジェクトには、アルバイトとして以下の3名の学生が参加しました。
男性 / 大学4年 | 広告代理店にクリエイター職で内定済み。 楽曲制作やゲーム効果音作成も個人的に手掛ける。 参加の狙い:コミュニケーション能力、特に要望をくみ取る力を磨く。 |
女性 / 大学4年 | 大学院進学と迷った結果、民間企業への就職を決めた学生。海外留学経験も持つ。 参加の狙い:相手に伝える力を伸ばす。 |
女性 / 大学3年 | Webデザイナー志望。 ゼミでは採用支援のショート動画制作企画に取り組んでいる。 参加の狙い:企業理解を深めつつ、採用広報の実務経験を積む。 |
「就活のリアル」と採用戦略上のポイント
学生がどのように情報収集を行い、企業を選び、採用広報を見ているのか。
「ミライカケハシプロジェクト」を通して、見えてきた就活の「リアル」。
本プロジェクトからは、「企業側が考える採用施策」と「学生の実態」には、意外なギャップがあることが見えてきました。
次の項目では、上記学生たちが採用広報に取り組み、企業に提案をした学生の「就職活動のリアル」と、それを踏まえた企業が視野に入れるべき採用戦略上のポイントについて紹介します。
就職活動における情報収集・応募行動の傾向
学生視点から見た、就職活動の情報収集・応募行動については、以下の傾向があることが見えてきました。
- 利用メディア:口コミサイトを中心に、TikTokやYouTubeなどのSNSも活用
- 初期段階の基準:給与・勤務地など最低条件でフィルタ
- 現実ラインの調整:理想条件から現実的条件に落とし込み
- 口コミの影響:社員や学生による残業実態・人間関係・成長環境などの口コミを重視
学生の情報収集行動を見てみると、求人条件だけでなく、口コミやSNSを通じて「企業のリアルな姿」を探っている様子がうかがえます。
つまり、学生は求人票の数字よりも、「働くイメージが持てるかどうか」を重視しているのです。
採用戦略上のポイント
学生は給与や勤務地などの最低条件をまず確認し、その後説明会や社員対応から応募可否を判断しています。
そのため、SNSや口コミサイトでの情報発信を 学生目線で自然に行うこと が効果的です。
単発の投稿ではなく、継続的に“なんとなく知っている企業”を増やす採用広報施策を意識すると、採用戦略にもつながります。
説明会・コミュニケーションで学生が注目するポイント
説明会など「企業と学生のコミュニケーションの場」については、実際には以下の傾向があることが学生による提案から見えてきました。
- 登壇形式の影響:1人登壇は雰囲気が伝わりにくく印象△
- 複数社員登壇:掛け合いや学生への軽い質問があると好印象
- WEB説明会の心理:カメラON/OFFルールの配慮が必要
- オフィスツアー・職場紹介:食堂や共用スペースなどリアルな雰囲気重視
特に、登壇形式については意外だった企業様もいるのではないでしょうか。
「必要な情報を伝えている」つもりでも、学生が本当に知りたいのは「雰囲気」であったことから、ここにミスマッチが生じてしまいます。
採用戦略上のポイント
説明会やコミュニケーションでは、学生が企業の雰囲気や人間関係を重視していることを意識しましょう。
複数社員による対話形式や軽い質問を取り入れることで、学生に安心感と好印象を与えられます。
WEB説明会でもカメラON/OFFの心理的配慮を行い、オフィスのリアルな雰囲気を伝えることで、学生目線での採用広報の効果が高まります。
採用サイト・SNS発信で学生に響く内容とは
多くの企業が導入しているであろう、採用サイトやSNS発信。
意外とこれらの媒体に対して学生が持つ「本音」を知る機会は少ないかもしれません。
実際に、学生たちは以下の点に注意が必要であると訴えています。
- SNSの好例:自社キャラクターの愛らしい/シュール動画、社員同士の自然な交流、オフィスコーデ紹介
- SNSの注意点:無理に踊らせる動画はマイナス印象
- 採用サイトの情報設計:箇条書き+数値・写真でリアルを伝える
- 給与・待遇情報:改善予定や見込みがある場合は明記すると信頼度アップ
一時期は、SNS上でダンスを踊る投稿も流行しましたね。
企業側は「雰囲気の良さ」「楽しさ」などを伝えているつもりでも、実は学生にとってはマイナス印象となってしまっていることがわかります。
実は、「好例」の項目にもあるように、「自然な交流」といった、実情・実態を学生は知りたいのかもしれません。
採用戦略上のポイント
SNSや採用サイトでの情報発信は、学生目線で自然体かつ世界観が統一されていることが重要です。
採用サイトなどの広報物は以下の様に記載しましょう。
- 休暇制度なら「年間休日120日+有休取得率◯%」のように数字で示す
- 福利厚生なら「社食あり」「住宅手当◯円支給」など具体的に記載
- 働く雰囲気は、社員写真や1日のスケジュール画像などを添える
条件・制度への考え方と内定後の心理
採用をする上で必須となるのが条件面や制度の掲載・アピールです。
各社様々な訴求点があると思いますが、どの様な点に気をつければ良いのでしょうか。
学生たちは、以下の点について、訴えをしています。
- 給与・年間休日:重視するが、最初に強調されると逆効果
- 転勤・制度説明:説明次第で印象改善、具体例や数字の提示が重要
- 福利厚生:抽象的よりも、金額・利用頻度・利用者事例の提示が好印象
- 内定承諾後の心理:内定後、SNS等を通じて内定ブルー状態になりやすく、承諾後のフォローも重要
給与や年間休日は、多くの企業がプッシュしている点かと思います。
実際に、学生にとっても重要な事項であることは認識しつつも、それを強調しすぎてしまうと、「それ以外に良いところはないのか」など疑心暗鬼に繋がってしまうようです。
採用戦略上のポイント
給与や制度を伝える際は、数字や具体例を交えて学生目線で分かりやすく説明することが大切です。
また、内定承諾後も学生は不安になりやすいため、面談や先輩社員との交流、社内イベントなどでフォロー施策を組み込み、安心感と信頼感を高めることが採用戦略上のポイントです。
企業の採用広報とのギャップ
本プロジェクトを通して明らかになったのは、企業が伝えたい情報と学生が求める情報にはギャップがあるということです。
企業が重視する制度や条件と、学生が実際に知りたい職場の雰囲気や社員の働き方は必ずしも一致せず、このズレを理解しないまま広報を行うと、学生に響かない採用施策になってしまいます。
本項では、企業と学生の間に生じる情報ギャップの具体例と、学生視点で魅力を伝えることの重要性について整理します。
企業が伝えたいこと vs 学生が求める情報
多くの企業は、学生に来て欲しいという想いから、どうしても自社の強みや制度、数字面の情報など、「アピール中心」に広報を行いがちです。
しかし一方で、学生は 職場の雰囲気や社員の様子、リアルな働き方を重視して情報収集していて、条件面だけで企業を選ぶわけではない様です。
もちろん、給与や年間休日などのアピール要素も確認しますが、過度な強調は学生にとって「魅力がそれだけ?」といった不信感に繋がるということにも。
このように、企業の意図するメッセージと学生が求める情報にはズレが生じやすく、採用戦略を考える上で重要な課題となっています。
学生視点で魅力を伝えることの重要性
企業が自社の魅力を学生に正しく伝えるには、学生視点で情報を整理し、共感を呼ぶ形で発信することがポイントです。
具体的には、社員の自然な交流やオフィスの雰囲気、実務上のやりがいなど、数字や条件だけでは伝わらない「働くリアル」を見せることが有効です。
こうした学生目線の情報発信は、採用広報の効果を高めるだけでなく、学生との信頼関係構築にもつながります。
つまり、企業の魅力を学生が共感できる形で伝えることこそ、採用戦略上の重要なカギとなります。
まとめ
今回の「ミライカケハシプロジェクト」を通して見えてきたのは、学生の就活行動や情報収集のリアルには、企業の想定と異なるポイントが多いということでした。
学生は「条件」だけでなく、社員の人柄や職場の雰囲気、会社の空気感といったリアルな「働くイメージ」を重視しており、求人媒体やSNS・採用サイトなど各種媒体を活用して何十社もの企業をスピーディーに比較しながら応募先を判断しています。
一方で、企業側はどうしても制度や実績などの「伝えたい情報」に偏りがちです。
そのギャップを埋めるには、学生の視点で自社を見直し、採用広報やSNS発信のトーン・内容を再設計することが大切です。
そうして「どんな人が活躍しているのか」「どんな雰囲気で働けるのか」といった「人と空気感」の見える情報発信をしていくことが、学生からの共感と信頼を高める強力な採用戦略になります。
R4では、こうした学生目線での採用戦略設計や採用支援全般を行っています。
採用戦略の再設計を通じて、企業の魅力をより効果的に伝えるお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
R4は採用課題に対する支援をしています
母集団形成、採用コストの適正化、採用代行など、
採用活動の「困った」をご相談ください。